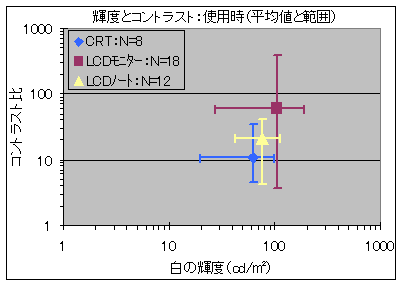
実際にユーザーが使っている状態での輝度測定値.輝度とコントラストはLCDモニター,LCDノート,CRTの順に高い値を示す.LCDノートは実際に使われている輝度の範囲は比較的狭い.
図7-1 輝度とコントラスト:使用時
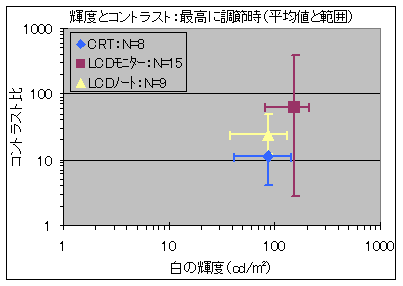
図7-2 輝度とコントラスト:最高に調節した状態
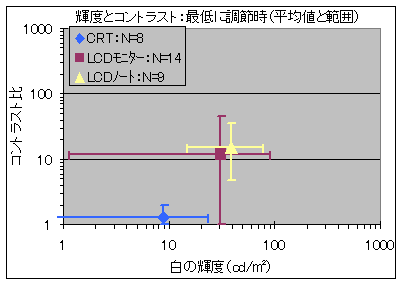
図7-3 輝度とコントラスト:最低に調節した状態
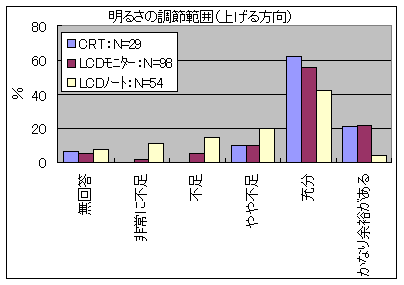
図7-4 明るさの調節範囲の評価:上げる方向
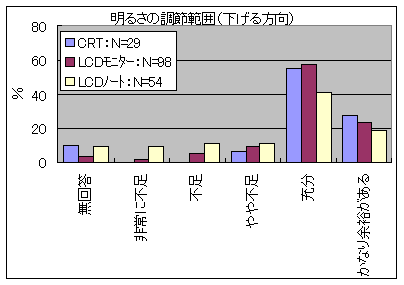
図7-5 明るさの調節範囲の評価:下げる方向
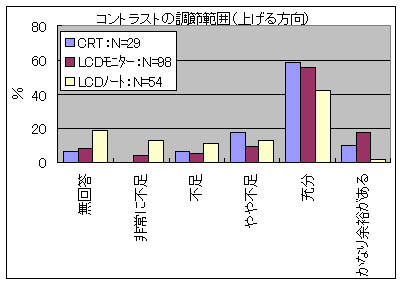
図7-6 コントラストの調節範囲の評価:上げる方向
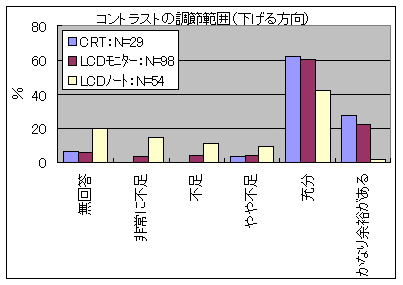
図7-7 コントラストの調節範囲の評価:下げる方向
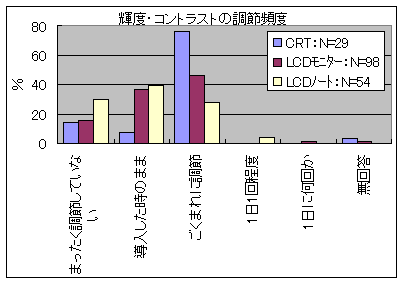
これは次の図7-9に示すようにLCDノートでは調節できない機種が約1/4もあることによると考えられる.
図7-8 輝度・コントラストの調節頻度
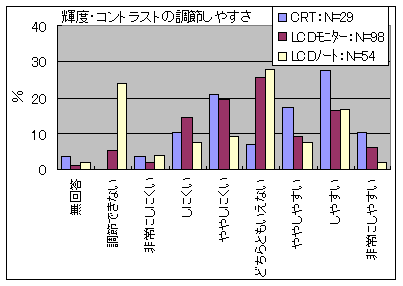
図7-11に示したようにそのつけはユーザーの視覚負担へまわされる可能性が高い.
さらに,
使用環境と作業空間の図8-3で示したように,LCDモニターよりLCDノートの方が画面照度の範囲が広い.むしろノートの方が調節の必要性が高いといえる.
図7-9 輝度・コントラストの調節しやすさ
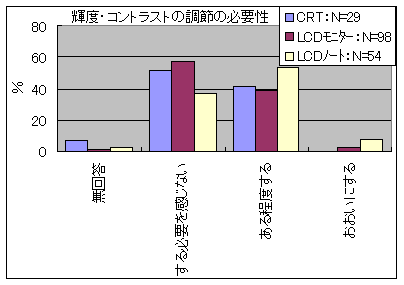
ユーザー自身も調節の重要性に気づいていない場合もある.環境条件に合わせた輝度とコントラストの調節は必要である.
その重要性は,次の図7-11に示したとおりである.
図7-10 輝度・コントラストの調節の必要性
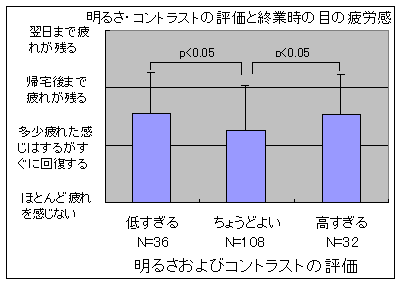
図中の「低すぎる」は,明るさもしくはコントラストの評価で3以下すなわち「やや低い」以下の評価をした回答者群,「高すぎる」は同様にいずれかが「やや高い」5以上の評価をした回答者群,「ちょうどよい」は明るさコントラスト共に「ちょうどよい」すなわち4の評価をした回答者群である. 明るさとコントラストで評価が逆方向の回答者は数名いたがここでは集計から省いた.
輝度とコントラストの調節の重要性を明示しているデータである.
図7-11 明るさ・コントラスト感と終業時の目の疲労感
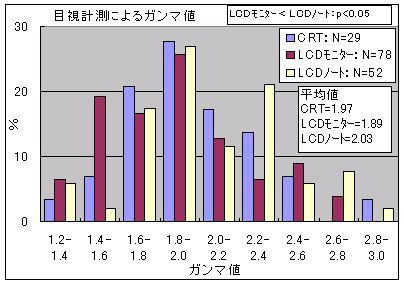
輝度が最大の25,50,75%の3点と100%輝度における階調レベル値を求めガンマを算出し平均値をとったもの.
目視によるガンマ値の精度がどの程度であるかが問題だが, いずれも2前後ではあった.また,LCDノートはLCDモニターより有意にガンマ値が高かった.その理由は不明.
図7-12 目視によるガンマ値の測定結果
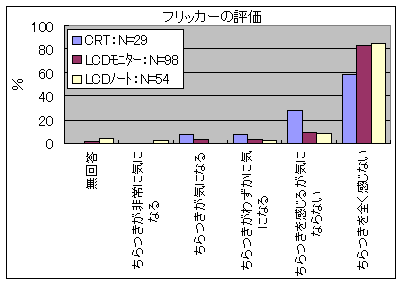
しかし,極端な観察条件での調査ではあるが,いまだに「わずかに気になる」まで含めると10数%のユーザーがフリッカーを気にしていることになる.おそらく,60Hzないし70Hzのユーザーであろう.90%のユーザーがちらつきを感じないレベルになるにはさらに高周波数化が進むであろう.
図7-13 ちらつき(フリッカー)の評価
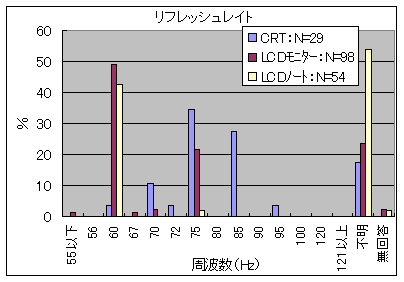
図7-14 リフレッシュレイト(図2-7と同一)